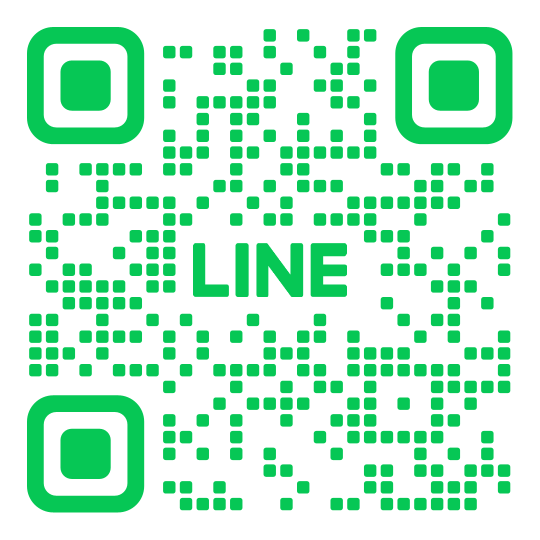【家の寿命に影響】防湿について『見えない所に結露させない対策』
高気密高断熱住宅に必須の【防湿】について
高断熱高気密住宅には【気密】と【断熱】以外にも大事な要素がいくつかあります。
その一つが【防湿】です。
防湿ができていないと壁内結露が発生し、家の寿命を縮めたりカビがはえる原因になります。
防湿について簡単に説明すると水蒸気を通さないようにする事です。
部屋の中の空気に含まれる水蒸気を壁の中や小屋裏に入れないようにする事が目的です。
以前気密についてお話しましたが今回の防湿はよく気密と混同されるんですが別のものになります。
気密は空気を通さないことですが防湿は水蒸気を通さない事です。
今回はそんな重要な防湿について解説します。
この記事を最後まで読むことで防湿について理解し、気をつけるポイントがわかります。
✔今回の内容
①防湿について
②防湿ができていないと何が悪いのか
③防湿の注意点とポイント
④最後に
①防湿について
防湿は部屋の中からでる水蒸気を壁の中や小屋裏に入れないようにする事です。
水蒸気の粒子はすごく小さいので例えば気密の為に合板で空気を通さないようにしていても水蒸気は通過していきます。
水蒸気を通さないように専用のシートなどを使って対策するのが防湿でその防湿した部分を防湿層と呼びます。
②防湿ができていないと何が悪いのか
【壁内結露】の原因になります。
【結露】というのは、水蒸気を中に含んだ暖かい空気が冷たいものに触れて冷やされた時に水滴ができるんですがその現象を結露といいます。
例えばビールのジョッキについている水滴や冬の窓ガラスについている水滴も結露の発生が原因です。
【壁内結露】というのは結露が壁の中や天井裏の見えない所で発生する事です。
見えないところで結露が起こるので気づかない内に壁の中の柱や梁の木部が腐ったりカビが生えたりする事で家の寿命を縮めたり健康に悪い家になる原因になります。
壁内結露に気付くころには、被害が広がっていて大規模な修繕が必要になることもあります。
この壁内結露が防湿ができていない住宅では特に冬に起こりやすくなります。
冬場に部屋の中の水蒸気が壁や天井を通過して冷えた外壁側の壁や小屋裏の部材に触れる事でその部分に結露が発生して壁内結露がおこります。
防湿がきちんとできていると部屋の中の水蒸気が壁の中や小屋裏に入っていかなくなるので壁内結露を防止する事ができます。
③防湿の注意点とポイント
✓基本的なポイント2点
1.壁の室内側に防湿層をつくる
2.防湿層を途切れないように連続してつくる
1.壁の室内側に防湿層をつくる
気密は合板等で外壁側に気密ラインを作る事ができるんですが、それだけだと室内の水蒸気が壁の中に入ってくる事はふせげないので室内側の壁の内側に防湿シートなどで防湿層をつくる必要があります。
室内側に防湿層がないと気密性能は良いのに、壁内結露が発生してしまうという事がおこります。
2.防湿層を途切れないように連続してつくる
防湿層は途切れないように連続してつくる必要があります。
防湿層に途切れているところがあるとそこから水蒸気が壁の中に入り壁内結露が発生する原因になります。
破れや隙間があったら防湿層が途切れるので、防湿シートの破れ等はテープで補修する必要がありますし、コンセントや配管の周りもテープやパッキン材などを使って隙間や穴がないようにする必要があります。
壁と天井のシートの継ぎ目部分も間があかないように重ねて取り付ける必要があります。
さらに注意するポイントとして例えば壁の断熱材には袋入りのグラスウールがよく使われていますが室内側についてるシートが防湿層の役割をしているのでそれを隙間なく柱や間柱にとめ付けないといけません。
下の画像の例だと断熱材の下に隙間が空いていて、防湿シートもきちんと止めつけられていないのでこのままだと壁内結露がおこる可能性があります。

防湿層をつくる方法には防湿シートを張る以外にも防湿の加工がされた吹付タイプの断熱材を使うなどのバリエーションがありますが、上記の2つのポイントは共通して大切な要素です。
④最後に
気密性能は現場検査でC値という形で数値がでるのできちんと施工されているかわかりやすいのですが防湿がきちんとできているかは数値ではでてきません。
その為C値の数値が良いからといって防湿もできているとは限らないので注意が必要です。
特に防湿層を連続して隙間なくつくるという部分は簡単に説明しましたが、実際の建物には凹凸や開口や壁と天井の取り合い部分等があるので色々注意して施工しないといけません。
気密と同じで丁寧な施工と防湿の事を理解している施工者がいて、それを現場監督がちゃんとチェックできている事が重要になります。
気密や断熱の事も別記事で解説していますのでチェックしてください。
断熱についての解説⇒https://www.wakitakoumuten.com/blog/id_671/
気密についての解説⇒https://www.wakitakoumuten.com/blog/id_635/
それでは今回も見て頂いてありがとうございました。
しつこい営業いたしません! 小さな事でもご相談ください
- ご相談・お見積りは無料です!050-3649-3470
- メール
- LINE